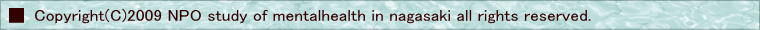【はじめに・・講師紹介(長崎大学小澤寛樹教授より)】
長崎大学病院精神科では、精神科医、心理士、看護師、小児科医、作業療法士など、多職種のチームを組んでいます。
発達障害はもちろんですが、それに伴う、例えば子どもの鬱というような二次障害、あるいは小児科で対応が難しい妄想状態、激しい興奮がある場合など、連携(リエゾン)をとって取り組んでいます。これは結構、全国的にもユニークです。
また、外国では必ず内科と小児科があるように、精神科でも成人の精神科と子どもの精神科がありますが、日本は全くないという状況、専門機関によっては、受診するために予約をするがかなり待たされるという現状があります。
最近、長崎で5000人規模の調査をやって、中3になると特に女の子の3割くらいが欝病予備軍の状態がアンケート調査では出てくるのがわかりました。
また、最近新聞にも載りましたが、ちょっと何か声が聞こえるとか、他人に操作されてるんじゃないか、スパイなんかが自分をつけてるんじゃないかとか。僕らで言うと統合失調症のような症状を見せる子がいないか調べてみました。
その結果、「声が聞こえますか」、「何かテレビで自分の噂をしているようなことが聞こえますか」、というような質問をすると、少なくとも1個に丸をした子が16%いたんです。
ちょっと驚きなんですけど、今の子どもたちはいろんな意味で大変な状況かなと思っています。
岩永先生は、今、長崎大学の作業療法学科の準教授で、この発達障害あるいは子どものいろんな問題の長崎の第一人者と言えます。第一人者というのは普通、教室にいて誰かが相談に来たらコメントするものらしいんですけど、その点岩永先生は違って、いつもいろんなとこで講演したり、サポートしたり、フットワークの良い、ほんとに長崎をすべからく駆け回って子どもたちの問題を一生懸命対応してくれている先生です。本日は、いろんなお話を伺いたいと思います。
●気になる子どもたちがいます
私は、大学の方には席を置いていますけど、最近はやはり学校とかに出向きお子さんと関わる機会が多いです。
私ひとりで何かしているわけではなく、現場の先生方、あるいは親御さんと話をしながら、現場の方々がお子さんを支えていく時に、私なりにできることに関わるというように、私が主役というよりは現場の先生に頑張って頂いている所にかかわらせて頂いています。
現場では、落ち着きのない子どもさん、キレる子どもさん。人付き合いの苦手な子どもさんというのはたくさんいらっしゃいますし、こういう子どもさんの対応において、親御さんはもちろん学校の先生、保育園の先生方も、非常に困惑されている現状に出会います。
こういうお子さんが、どの地域にも、どの学校にもいらっしゃるかと思います。こういう子どもさんたちに対する対応というのを地域の人すべてが知ってですね、的確な対応をしていけば、御本人たちも、保護者の方達ももっともっと楽になれると思いますし、社会がもっと良くなっていくんじゃないかなと思います。
●気になる子どもたちは発達障害では?
早速話の方に入っていきたいと思います。気になる子ども達はどの地域にもいらっしゃると思います。子育てが終わられた方もいらっしゃると思いますけど、そういう方も、ご自分が子どものころにこういう子が周りにいたとか、地域にこういう子どもがいることがすぐお分かりになるかと思います。
落ち着きがないお子さん、なかなか教室で座ってないとかですね、そういうお子さんいらっしゃいます。それで乱暴な行動が目立つ。すぐにキレてしまって、感情的になるお子さん、わがままなお子さん、ルールが守れないお子さん、友達とのトラブルが頻繁にあってなかなか仲良くできないお子さんもいらっしゃいます。こういうお子さんがいると、やはり大人は躾がなっていないんじゃないかと思って、頭ごなしに叱ってしまうことが多いんじゃないかなと思います。
でもこういう子どもたちはですね、調べていくとここに書いているような発達障害という状態であることがわかります。自閉症やアスペルガー症候群、多動性障害などですね。
多分、どこかでご覧になったことがあると思うんですけども、馴染みがない方もいらっしゃるかもしれませんので、どういうタイプのお子さんかをビデオでお見せします。
- ビデオ -
少し発達障害のお子さんのイメージがわいたかと思います。
やはり、大きな特性として外見上何ら障害があるように見えないというのがあります。これは一見メリットのようですが、誤解を生むきっかけとなっています。
●発達障害とは?
発達障害というのはですね、今出てきた自閉症とかアスペルガー症候群やその他に学習障害や注意欠陥多動性障害などの問題もあるんですが、脳の何らかの働きの違いによって、行動や対人や学習の問題も出てくる人たちのことです。
この発達障害という言葉は、法律の中ではきちんとした位置づけがなかったんですけども、平成17年(2005年)に「発達障害者支援法」というのができて、発達障害というものが位置づけられました。
この法律ができる前までは、アスペルガーとか注意欠陥多動性障害と呼ばれる人々は法律の中では障害者としてきっちり認められていなかったのですね。最近やっとこの子どもたちが障害を持っていて支援が必要なんだということが法律の中でも謳われるようになってきました。
さきほどのビデオで出てきた子どもの様子を見るとですね、わがままな子どもさんに見えたかもしれませんけども、ああいうアスペルガーの人たちの脳の活動を測ってみると違いが見えるんです。
これはですね、恐れの表情を見てる時に、脳がどういう活動をしてるのを調べている研究ですね。この「A」で示されている脳の画像はですね、障害のない人たちの脳です。
彼らには「定型発達」という言葉を使いますけども、定型発達というのは障害のない人たちのことです。定型発達の人たちは恐れの表情を見た時に脳の中にある感情脳が働いているんですね。この感情脳が働くと、悲しんでいる人を見て自分も何となくじんわりと悲しくなってくるもらい泣きをしてしまうようなことがおこるんですね。恐れの表情を見た時に、その人の気持ちを心で理解しているような状態です。
でもアスペルガーの人の脳がこれなんですけども、脳の違うところが働いています。感情脳があまり働かずに、形を認識したり、記憶と照合したりするところが働いています。
「眉間に皺が寄ってるから怒ってるのかな?」とかですね、理屈で考えようとしているのかもしれません。なかなか感情で相手の心を受け取るのが難しいということが、こういう画像からつかめるかと思います。
なかなかですね、人の気持ちが読めないと、どうしてあなたはわからないのと子どもを責めてしまうかもしれませんけど、脳が違う、認知が違うお子さんがやはり子どもの中にある一定の割合でいらっしゃるんですね。
そういう子どもたちが今どのくらいいるかというと、文部科学省はですね、通常の学級の中に発達障害の特性をもつ子どもたちが6.3%いるという結果を出しています。
これは昔でいう特殊学級とか養護学校のお子さんを含んでいません。通常学級の中にこれだけいるということがわかっています。
ただしこの数字も、まだ精神科領域で出されている数字と比べると少ないです。通常学級の中に10%くらい支援が必要なお子さんがいると言っても過言じゃないと思います。
今こういう風に支援が必要な子どもたちが、特殊学級じゃなくて通常学級のなかにもいることが分かってきていますので、平成19年に法律が改正されまして、学校教育の中でこういう発達障害の特性を持つ子どもたちをしっかりサポートしていこうというような体制が取られるようになってきております。
●注意欠陥多動性障害(ADHD)
では、今日は発達障害の中にもいろいろあるんですけども、大きく3つの障害を取り上げたいと思います。まずその一つが「注意欠陥多動性障害」ですね。これはADHDとも略して言われます。これはですね、タイプが3つあります。
「多動衝動優勢型」と「不注意優勢型」と「混合型」の3つのタイプですね。
多動衝動型というのは、クラスの中でうろうろしてしまうお子さん、教室から飛び出してしまうお子さんですね。落ち着きなく動き回ったり、あと、ちょっかいが多いと。やりたいことを抑えられない自分を抑えるのが苦手な子どもたちですね。「ドラえもん」の「ジャイアン」はご存知かと思いますが、ジャイアンは診断をつけると、ADHDの多動衝動型か混合型になります。
不注意型というのは、「のびた君」がこのタイプになります。のびた君に診断をつけると不注意型になります。多動衝動というのは目立たないんですけども、ボーっとしていて話を聞いてない、やってる途中で集中力が切れる、やる気がないと、こういうふうに怠け者と思われやすいタイプですね。
ではこの特性を併せ持ってるのが「混合型」です。ジャイアンとかのびたがADHDの範疇にはいると聞くと、かなりこういうタイプのお子さんはいるなとわかりますし、発達障害というのはどこにでもいるなというのはわかります。
結構アニメの主役はADHDの人が多いですね。クレヨンしんちゃんなんかもその範疇にはいります。結構有名人にも多いですね。ここに出てきてるケネディとかエジソンといった人たちもADHDだと言われています。野球で有名な新庄とか、長嶋茂雄とかもそういうタイプではないですかね。長嶋茂雄が一茂を球場に忘れて行ったというエピソードを聞くと、なるほどな、と思います。
すごくあるところには集中して力を発揮することはあるんですけども、学校教育の中ですべてのものにおしなべて注意を払うというのが苦手ですね。ある程度なんにでも注意を払うというのが苦手です
。
学校での特性として、授業中歩き回る方が多いですね。低学年の頃は立ち回るという問題がよく目立って、担任の先生が非常に指導に苦慮されている場面があります。こういう風になってくると、大きな多動性というのは減ってくるんですけども、座った状態での多動ですね、そわそわしたり手混ぜをしたりすることがあります。
そして先生の話を聞いていないと。それで注目してもらうのが大好きな子が多いですね。ヒーロー願望が強い子が結構多いですね。何回も何回もあててもらおうとして、先生にあてられたそばから手を上げてあてないと怒るというお子さんもいらっしゃいます。お友達へのちょっかいというのもすごく多いので、先生がしょっちゅう叱っているという現状があります。
中には感情のコントロールが苦手なお子さんもいらっしゃいまして、カッとなってすぐにキレやすいお子さんもいらっしゃいます。整理整頓が苦手で、机の中が雑然となっていることが多いですね。不器用なお子さんも多いです。そのため文字や製作が雑になってしまうお子さんもいらっしゃいますね。
ADHDは3から8%いるんじゃないかといわれていますけど、最近の調査ではもっと多い数値が報告されています。これはアメリカでのかなり大人数を対象にしたデータなんですけど8.7%という数字が出ています。11人に1人はADHDであるというデータですね。どこの学校、どこの保育園にもいるということがわかります。
また、大人にもいるんですね。大人ではきちんと診断がつく方は5%くらいと言われています。ただ診断はつかないけれども、ADHDっぽさを持っている方はもっともっといますので、トータルで10%くらいになるのではと言われています。
「片付けられない女」という本がありますよね。片付けられない女とか同時進行できない人とか、片付けられない男もいると思いますけど、その範疇に入る方っていうのは結構ADHDの特性をもっている方が多いです。診断がつくかつかないかは別にして、そういう特性を持っている方は少なくないですね。
あれこれ興味を持って飛びつくけど全部中途半端になってしまうのはADHDの特性を持っていると起こりがちなことです。私にもそういうところがあるので、ADHD向けの本を読んでうまく生きていこうと努力していますけれども、ADHDの人たちは先生の言うことをよく聞いてくれないので、特にわがままだと思われやすいです。でも彼らもやっぱり脳の機能の違いがあって、行動のずれを起こしているんですね。
脳の中には「大脳辺縁系」と呼ばれる欲求を引き起こしたりする本能を司る部分があります。ここで食べたい、動きたい、何かしたいという衝動が起こるとまず仮定してください。ここで起こった衝動をすべて表に出してると、どうしても不適合が多くなります。
だから定型発達の人たちはこれを「前頭葉」と呼ばれるところでコントロールしているんですね。別の図に置き換えて考えてみると、アクセルとブレーキが定型発達の人たちはバランスよく使われていると思ってください。
外で遊びたいという欲求が子どもの中で生まれたとします。そこで前頭葉が働いてですね、ブレーキをかけると。今授業中だから駄目だと。そうすると外で遊びたいと思っても、ちゃんと授業中はその場に応じた行動ができるようになります。
でもADHDのお子さん方はですね、前頭葉の方の働きがうまくいかないことがあってですね、外で遊びたいというアクセルが踏まれたときブレーキがうまくかからないことがあるんですね。だから出ちゃダメだとわかっていても飛び出してしまう。たたいちゃダメだと分かっていても自分を止められないということが起こってしまいます。
だから全部許していいというわけではないんですが、どうしても脳の働きの違いがあって、こういうふうな特性が出ているんだとまずは理解すること。
そして、同年齢の子どもたちと同じ目標を立ててしまうとなかなかブレーキが弱いので、周りの子どもより失敗が多くなってしまいます。だから目標を変えてあげるということが大事ですね。
具体的にはイスに座っときなさいというふうに言った時になかなか自分をコントロール出来ないお子さんがいたとしたらですね、椅子から立つのは仕方ないけども、教室から出ないようにしようという風に、道路を広げてあげるんですね。それはちゃんと約束守ってねというふうに指導していくと。
子どもが達成可能な目標をかかげてあげて、それは守らせるよう頑張らせるという指導が大切になってきます。他の子どもとおんなじ目標にしてしまいますと、先生は何回も怒ることになってしまいますし、子どもも嫌な気持になってしまいます。
どうしてもブレーキが効きにくい子どもたちは簡単に叱られてしまいます。
ときどきそういう風に大人たちから特性に合わない指導をされてきた子どもたちは、あまり良くない発達をしてしまうことがあります。
「DBDマーチ」というんですけども、ADHDのお子さんの中で、周りに対して反発しやすいお子さんが大人から叱られ続けると反抗挑戦性障害となります。非行のような行動なんですけど大人の言うことを聞かなくなったりします。
ADHDのお子さんすべてがこうなるわけではありません。大人が子どもを追い詰めてしまうと、子どもを認めないということになってしまうので大人が敵になってしまうんですね。ADHDのお子さんで状態が悪い子は大人をなかなか信用してくれないことがあります。
ADHDのお子さんが中学生くらいになると、周りとの会話も少なくなり、学校に行くと生徒指導の先生から帰るまで怒られることがあります。
大人との居場所がなくなり、そういう彼らが居心地良く感じるのは不良グループなんですね。学校では疎外されててもそこに行くと居場所があり、リーダーにもなれるんですね。そこに行くと、大人の言うことを聞かなくなるようになります。大人たちが子どもたちの特性に合わせた指導をしていかないとこのようなことが起こることがあります。
ADHDみたいに言うことを聞かないお子さんがいたら厳しくすればいいと仰る大人の男の方がいらっしゃいますが、その結果子どもたちもつらい状況に置かれることも知っておく必要があります。そういうふうに大人たちが間違った指導をしていくと、子どもたちからしっぺ返しを食らうこともあります。
エネルギーが外に向かっていく人もいますが、多くは内に向かっていき鬱状態になる方もいらっしゃいます。やはり早期から子どもたちに合った指導をしていき認めていくといった対応が必要なんじゃないかなと思います。
●広範性発達障害(自閉症・アスペルガー症候群)
次は「広範性発達障害」です。この中で、後で「自閉症」と「アスペルガー症候群」の説明をいたします。自閉症は対人関係などに問題があるお子さんが多いです。自閉症は広範性発達障害に含まれる障害です。広範性発達障害は、自閉症と関連する障害で、広義の自閉症だと思ってください。
広範性発達障害の中にはアスペルガー症候群も入っています。アスペルガー症候群のお子さんは良くしゃべるし、知識もあるため一見普通のお子さんに見えます。
それと広範性発達障害は男の子に多いことも覚えておいてください。5対1くらいで男の子の方に多いですね。広範性発達障害は100人に1人というデータが出ています。
長崎県で私も調査をしていますが、2%くらいのデータが出ていますね。以前よりも増えていると。アメリカでのデータを見てみると、広範性発達障害の患者さんは増えていることが分かります。これは、診断技術が上がったということが原因だと思われます。
支援する方も多くの人数が必要になってきているという現状があります。
自閉症の説明ですが、おおまかに言うと対人相互作用に問題があると。相手の気持ちを理解して合わせて行動するというのが苦手ですね。それで、言葉や身振り表情などのコミュニケーションが苦手と。言葉の遅れも問題となりますが、それ以上に非言語コミュニケーションが苦手という問題もあります。
聴覚障害のお子さんは相手の表情を読み取り、一生懸命身振り手振りでコミュニケーションを取りますが、自閉症の子はそういうのが苦手です。興味価値観が偏っていて、こだわりがあると。同じお茶碗じゃないと食べないとか、同じ道じゃないと通らないとか、スケジュールの変更を嫌うなどです。偏食な子もいて、白いものしか食べないとか、ラベルにこだわっていて、メグミルクは飲むけどおいしい牛乳は飲まないという子もいます。
自閉症の子どもの5割は精神遅滞を伴います。IQ70以上のお子さんは高機能自閉症と呼ばれていまして、通常学級の中にいることが多いですね。それで社会の中で福祉的な支援を受けられない方が多いです。
こういう方々が就労するとき困難を伴います。対人関係が苦手なので営業職に就くと失敗して他の精神疾患を持ってしまうことがあります。
アスペルガー障害は自閉症からコミュニケーション障害を除外し、知的能力の遅れがないものをいいます。言葉の遅れがない障害をアスペルガーだと思ってください。
彼らは周りから障害だと思われないことが多く、そのため様々な問題が起こります。彼らは他人と関わりを持とうとしますが、距離感をうまくつかめず失敗してしまうことがあります。それで友達との関係がうまくいかないと。
仲間がいないため、抑うつ的になってしまうことがあります。常識が分からなく空気が読めないという問題もあります。また勘違いによるトラブルも多いです。ですが、大人との関係を持ちやすい子もいます。お友達がいないため、大人に行く場合が多いですが、そのような場合でも話し相手になって心を満たしてあげることも必要かなと思います。
相手に合わせるのが苦手なお子さんもいます。周囲からどう思われてるか気づけないお子さんもいます。自分の言動行動が周りからどう思われるかを気づけないんですね。周りの大人が教えてあげることも大事ですね。またしゃべり方が他の子どもと違い、大人びていることが多いです。また表情の読み取りが苦手なお子さんもいます。
特定のことに拘るというのも特徴ですが、知能が比較的高いお子さんは学術的なものにこだわる子が多いです。
ノーベル賞を取るような方でこういう方は多いですね。アインシュタインもそうですし、ニュートンもそうだと言われています。ビルゲイツも実はアスペルガーだという噂がありますね。シリコンバレーなどでは自閉症の子が多いですが、これは親にも自閉症が多いということですね。
価値観が違うという方もいますね。褒められることや報酬などに興味がないことも多いです。ファンタジーにひたる方も多いですね。不器用で、聴覚や触覚の感覚過敏が見られるかたもいますね。広範性発達障害の子は他の人の気持ちを理解するのが苦手です。
この「サリーとアンの課題」をさせるとそれがわかります。中学生だと解けることが多いですが、保育園や小学校低学年のお子さんは解けないことが多いです。
この課題というのは、「サリーが籠の中にボールを入れました。そしてサリーは部屋の外に出て行きました。そのすきにアンはこっそりとボールを籠から箱の中にボールを移しました。そして部屋の外に行きました。サリーが戻ってきました。ボールで遊ぼうと思っています。どちらを探すでしょう。というものです。
ほとんどの方は「籠」と答えますが、自閉症の子どもたちは箱だと答えることが多いです。それは、サリーの気持ちを理解できないからこのように答えてしまいます。自分が知っていることは相手も知っているだろうという考えがあります。
他の人には別の人格があるということを知らない子もいます。
こういう簡単な課題でも失敗してしまうお子さんがいます。皆さんはサリーが入れ替えられてるところを見ていないから知らないだろうと考えますが、人の気持ちを読むという認知機能がないと難しいものとなります。その認知機能が「心の理論」というんですけども、その障害を持っているのが自閉症の子どもたちです。ですので、周りの人々が言語化して教えていく必要があります。
冗談や嫌みがわからない子もいます。大学病院でも使われる検査ですが、
「さとる君は水たまりに飛び込んで遊んでいます。泥だらけになって帰ってもお母さんは怒らずきれいな洋服を着ているわねと言いました。」こういうストーリーを子どもたちに読んでもらって、クイズに答えてもらいます。
「さとる君はきれいな服を着ていますか?」と聞くとたいてい「いいえ」と答えます。
どうしてお母さんは「きれいな服を着ているか?」と言ったかを聞くと、「この泥が模様に見えたんじゃないか」と答える人もいます。ときどき正常の知能のアスペルガーの子もそう答えます。お母さんがきれいだと言ってるから、きれいだと思ってると捉え、「嫌味」とわからないことが多いです。
言葉を辞書通りには理解できるんですけど、人と組み合わせて理解することが苦手ということです。嫌味とかは結構辞書とは正反対の意味になることが多いですよね。その人の言ってる意図を理解しないと、ちゃんと理解できないことが多いです。ですから結構、冗談や嫌みを理解できなくて問題になる場合があります。
ですから周りの人は、最初に「冗談です」とか「嫌みです」と付け加えてから言う必要があります。そして、その意図を説明してあげないとわからないことが多いです。
広範性発達障害の人たちは感覚に問題があって、騒々しい音で混乱したり、散髪、洗顔、爪切りを嫌がるという人が70パーセントもいます。歯医者さんでパニックになってしまうお子さんもいらっしゃいます。脳の構造が違うため、周囲の音に敏感になってしまい苦しみを感じてしまうお子さんもいます。
●発達障害の子どもをとりまく現状
今、ADHDや自閉症、アスペルガーの説明をしてきましたけど、子どもさんの特性だけを掴むんじゃなくって、周りの反応も含めて理解していくことが必要です。
発達障害に関わっている大人たちが陥りやすいのは、性格の問題やふざけ、わがまま、不躾と考え、叱る厳しく指導する場合によっては放っておくなどして、その結果子どもを追い詰めてしまう、時には親御さんも追い詰めてしまうことにもなります。
発達障害の周りの子どもたちも、外見上何も障害が見えないため、その子がテストで0点を取っていたり、パニックを起こしていたりするとちょっかいを出してしまうことがあり、いじめに発展することもあります。そのため、子どもたちは元の障害の上に二次障害、三次障害が生まれます。
実は精神科の方で問題になるのは二次障害、三次障害の方です。
周りの人々が間違った対応をすると、子どもたちを追い詰めてしまい、結果的に情緒不安定などを引き起こしてしまうことがあります。
「非行」の問題や、最悪の場合「PTSD」になってしまうこともあります。あと、「不登校」になるケースもありますね。勉強の問題、お友達との関係、先生から言われたことが気になって不登校になるといったケースがあります。不登校になった子どもたちに正しい対応をしないためひきこもりになってしまう場合があります。
早い対応、適切な対応をすることによって二次障害、三次障害を防ぐことができます。ですので、早めに発達の問題に気づいてやって、適切な対応を周りがやっていくことが大切となってきます。
「虐待」との関係も指摘されてまして、虐待が見られる子どもの55%が発達障害だというデータが出ています。
特に知的障害が伴わない、一見何も障害が見られない子に虐待が多いです。保護者の方々は子どもが言うことは自分の責任だと感じ、つい躾が厳しくなりがちです。
ですので、子どもに診断が付いた時に保護者の方々が虐待を止めるケースが多いです。診断がしっかりと付き、周りの人々が子どものことを理解すれば自然と虐待は無くなっていきます。
こういう問題は地域の人々も知っておく必要があると思います。広範性障害の人たちは二次障害、三次障害で精神疾患を伴うことがあります。
気分障害が36%、不安障害が42%も見られると。解離性障害という、いわゆる多重人格も5%近くみられます。70%の人が抗うつ剤を飲んでいることもあります。
発達障害の人たちは大きくなると社会にうまく適応できなくなり、追い詰められて精神疾患の方に傾いてしまうことがあります。こういうケースの中には早めに対応していればもっと違うことになったのではというケースも少なくありません。
早めに気づいて対応して二次的な精神疾患を防ぐことが大事です。発達障害の子どもたちを理解していくときに、こういうことも知っておいて欲しいなと思います。
●発達障害の診断
発達障害の診断というのは難しいんです。例えば注意力が低い人といっても、どの程度までかを決めるのは難しいことです。どうしても診察する人によってぶれてしまいます。
ボーダーラインで診断がつかない子どもでも、地域や社会の中で不適応を起こしてしまうことがあります。こういうボーダーラインの子どもたちが地域の中にたくさんいます。
今日は発達障害のことを話してきましたけど、切れる子どもたちの中にはこのように診断がつかない子どもたちもいます。
このような子どもたちにも実は発達障害の子どもたちと同じような対応をしたり、支援をしていく必要があると思います。発達障害を理解することで、診断がつかないけど切れやすい子、落ち着きがない子みんなに支援がうまくいくことがあります。
こういうことを見ていくと、定形発達の子と発達障害の子の間には明確な境がないことがわかります。
発達障害は身近なものだと、もしかしたら私たちもその範疇に入るかもしれないということを思っていただければ、もう少し発達障害の子どもたちを理解できるんではないかと思います。
●発達障害と隣り合わせの問題
次は、発達障害と隣り合わせの問題も話したいと思います。「反応性愛着障害」という問題です。
発達障害の一部と言われているんですが、虐待などの不適切な養育を受けた子どもに、多動、攻撃性などの問題行動を生じることが多いものです。
「抑制型」と「脱抑制型」に分けられます。「抑制型」は人に対して無関心で、広範性発達障害に非常に類似した特性を持っています。「脱抑制型」は誰彼かまわずべたべたと無差別に関わって、ADHDにきわめて似た特性を持ちます。
虐待を受けているお子さんが、この発達障害っぽい特性を示すことがあるんですけども、そういう子どもたちは環境を変えることによって、行動が変わっていきます。
発達障害の要因によって問題を起こすこともありますが、このように環境によって問題を引き起こすこともあります。
これまでは環境説を重視していたんですね。親のしつけが悪いとか、環境が子どもを作っていると思っていた方が多いと思いますが、子どもたちの脳の特性によって問題が起こるということを考えておく必要があります。
原因はどちらにせよ、子どもたちの特性に合わせて周囲の大人たちが対応を変えていくことが大事で、二次障害、三次障害を防ぐことが大事です。対応に関しては環境が一番大事ということは間違いないですね。
●発達障害支援で大切なこと
では、私たちが何をしていくかが大事かを話したいと思います。
発達障害支援で一番大事なことは早期に気付くことです。できれば「1歳半検診」で気付くのがいいですね。
しかし、私も検診をしているのですが、全てのADHDに気付くことは難しいですね。
やはり、軽いADHDの子どもには気付かないこともあります。そういう子どもたちは保育園や学校、地域の中で気付いていってあげなければと思います。
発達障害に対して理解のある大人たちが増えていけば、彼らたちに気付いていってあげることができます。
気付くだけではなく、その後に学校で特別支援教育が必要となってきます。子ども達の特性に合わせた支援を行っていくことで二次障害を防ぐことができますし、必要な力をつけさせることができます。
特に一貫性のある指導が必要です。まだまだ、支援が足りないですが、大人になっても支援するシステムも必要です。
お金の管理ができず借金をしてしまうケースや、騙されて契約をしてしまいそれを解約できないなんていうケースもあります。ですので、大人たちをしっかり支援しサポートする体制がまだまだ必要なんじゃないかなと思います。
一般社会に発達障害に関して啓発していく必要があるんではないかなとも思います。親も二次障害を負いやすいので、親もサポートしていく必要があります。虐待家庭を見ていくときに実は親にも支援が実用だったというケースもあります。
親を支えていくことによって虐待が収まっていくということも結構ありますので、子どもだけではなく親にも注目することが大事です。
まだまだ自閉症やアスペルガーの人達が社会の中で生きていくのは難しいです。
ニートの方が多く、就労が難しい状況です。アスペルガーや自閉症の場合、企業雇用の障害者枠に入るのが難しいのが現状です。ですので、法律や制度でも改善しなければならないのが現状です。
発達障害を、一般の方たちが理解していく、早期に気付いて適切な支援をしていくことが大事です。
●学校での対応
あと学校での対応も変わってきておりますので、そういうところからも始まっています。それに順じて大人たちも子どもたちに対して対応を考えていく必要があります。「特別支援教育」というのは平成19年(2007年)から始まっています。
発達障害は身近な問題だなということがわかっていただけたと思いますけど、通常学級の中に6.3%いるお子さんをどこかの訓練施設に集めて指導するってことをできるほど財源は豊かではないですよね。通常学級の中で彼らを支援していかないと追いつかない状況です。
だから、通常学級の中でも彼らを担任が責任をもって対応していく体制ができてきています。
これが「特別支援教育」なんですね。特別支援教育は学習指導要領に乗っかって教えていくだけではなく、子どもに学習を合わせるオーダーメイド教育でもあります。
●医療での対応
医療での対応ですが、ADHDのお子さんに対して最近良いお薬ができてまして、長崎大学のほうで小澤先生に診てもらえばいただけると思います。
ADHDのお子さんは前頭葉の働きが弱く、それを強めることで、多動を制御したりして、手助けとなります。
このように病院にかかれば、診断が付きお子さんの特性に合わせた薬も処方できるため、医療の方にもお越しください。
●身近な発達障害の子どもへの対応
発達障害のお子さんが身近にいる場合、どのような対応をするかということですが、叱って育てるより褒めて育てるということが大事になってきます。叱る前に良い行動を教えるということも大事になってきます。
あと、大人が子どもの話を聞く、しっかり対応するということも大事だと思います。大人はちゃんとやっているときは関わらずに、うまくいかないときに飛んできて叱ることが多いんですね。
問題行動が起こったときに叱るという考えよりもですね、正しい行動ができたら褒めると考えることが必要ですね。
問題行動をおこす子どもたちはいつも大人たちに叱られてばかりで、大人から監視されている気分になります。時には叱られすぎた子どもたちは大人たちが敵になってしまいます。
だから子ども達の行動をネガティブな場面だけでなく、ポジティブな場面でも注目してあげて褒めるということが大事となってきます。
やはり、自分の良い所を見ていてくれてる大人たちにはちゃんと信頼しますし、褒めてくれてる大人たちにはちゃんと心を開いてくれます。
でもほとんどの大人はこれをやり切れていないと。ほっといても正しく育つのが子どもだと思っています。ほっといても育つ子どももいますけど、中には配慮してあげないとまっすぐ育ちにくいお子さんもいます。
ですから、たくさん褒めるということも大事になってきます。まずは子どもたちなりに頑張っている行動を褒めてあげましょう。叱ることより褒めることからまずは入っていくことで、親子関係もうまくいき、問題行動も少なくなることがあります。
もちろん褒めてばかりではなく、叱るときには叱ることも重要です。9褒めて、1叱るというのが良いと思います。
また、子どもと二人っきりになる時間も必要です。十分に愛情を注ぐ時間を、愛情を感じられる時間を与えてあげることが大事です。子どもが大人を独り占めして満足する時間ですね。
あと、相談できる機関として色々ありますけど、もし心配なお子さんがいたら、児童思春期外来の方にお越しいただけたらなと思います。これで私のお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。
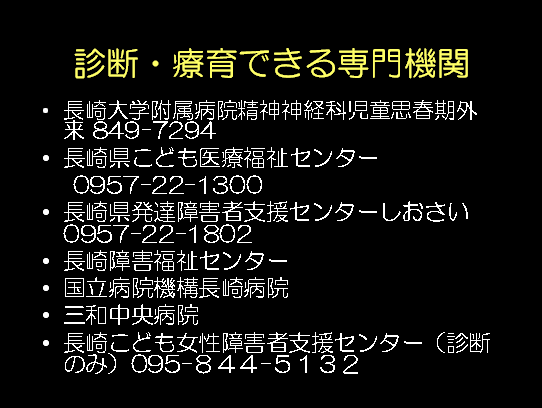
(お話:岩永竜一郎先生 平成21年9月16日 長崎歴史文化博物館にて) 上へ 上へ
|